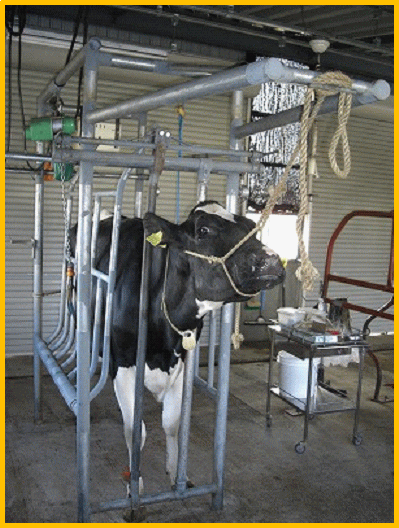平成26年10月9日、採胚予定日当日の朝、12ヶ月齢未経産ドナー牛が起立不能となり、重度の貧血を呈し死亡した。この未経産ドナー牛において、子宮摘出、採胚、胚培養、胚移植を行った。
・開腹と子宮・卵巣摘出の方法
左側を下にした伏臥の状態で死亡していたため、右膁部を約20cm切開し、腹膜を切り開いた段階で、腹腔内に多量の出血が貯留しているのを確認した。腹腔内を触診したところ、卵巣周囲に大きな血餅が付着しているのが確認出来た。左手で子宮間膜を裂き、子宮本体をなるべくフリーな状態にしてから子宮頸管を握り子宮を保持し、右手に鋏を持ち、外子宮口と外尿道口の中間辺りを切断した。左手で卵巣を保持しながら、卵巣を腹腔内で吊っている卵巣間膜を右手で持った鋏で切断。これを左右の卵巣で行ったのち、子宮・卵巣をまとめて体外へ出し、バットに移した。
・採胚と回収胚の処理
子宮を室内に運び、通常の採胚で使用するバルーンカテーテルを子宮角内に挿入・留置し、直視下での採胚作業を行った。25個回収し、内訳は、変性胚(変性部分が50%以上の桑実胚)4個、未受精卵20個、透明帯1個で、変性胚4個は38.5℃、5%CO2、20%子牛血清添加TCM199中で培養することにした。
・胚移植
培養24時間後に胚盤胞にまで発生が進んだ1個、及び48時間後に胚盤胞まで発生が進んだ2個を移植した。